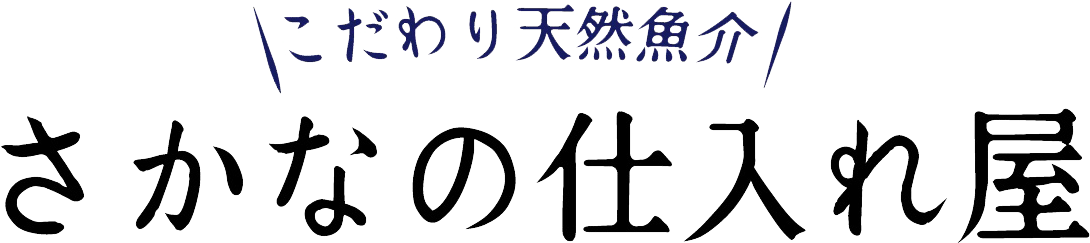子持あゆとは?その美味しさと梅甘露煮のおすすめ
秋の深まりとともに、鮎のなかでも特に珍重されるのが子持あゆ。
文字通り、お腹にたっぷりと卵(子)を抱えた雌の鮎のことで、「落ち鮎」とも呼ばれます。

この子持あゆの醍醐味は、なんといっても
・プチプチとした独特の食感
・濃厚な旨み
を持つ真子です。
卵を抱えるために脂が乗りきった身は、秋ならではの滋味深い味わい。
この旬の美味しさを丸ごと閉じ込めるために、昔ながらの製法でじっくりと煮詰めたのが甘露煮です。

「甘露煮」と聞くと、コテコテの甘~いものを思い浮かべるかもしれませんが、私が作るのは甘みを抑えて素材の持ち味を生かしたもの。
梅を加えることで、まろやかな甘さのなかに、ほのかな風味。
鮎特有の川魚の風味を上品に引き締め、後を引く爽やかな味わいに仕上げています。
また長時間かけて骨まで柔らかく煮込んでいるため、頭からしっぽまで、丸ごとお召し上がりいただけます。
・卵のプチプチとした食感
・とろけるような身
そのハーモニーは、一度食べたら忘れられない極上の逸品です。
ご飯のお供やお酒の肴に、この秋だけの特別な味わいをぜひご堪能ください。
魚匠直伝!子持あゆの梅甘露煮~美味しさの秘密は手間と厳選素材
子持あゆの梅甘露煮は
・新鮮な素材
・煮汁への徹底したこだわり
から生まれます。
新鮮な子持あゆを使うのはもちろん。
煮汁には福来純の料理酒とみりん、井上古式醤油や三温糖を使用。
素朴な鮎の持ち味を最大限に生かすため
一切の妥協を排した調味料選び
が品の良さを支えています。
実際の工程を一部ご紹介します。
魚匠流~子持あゆの梅甘露煮の炊き方
①ぬめり取り

市場で仕入れてきた新鮮な子持あゆを軽く塩でもんでぬめりを徹底的に落とします。
霜降りをしないため、ヒレまでしっかりぬめりを落とさないと、仕上がりの臭みの原因となります。
軽くお腹を押して排泄物を出しておくのも重要な下準備。
②素焼きにする

ここでのポイントは弱火でじっくり

ヒレを焦がしてしまうと、仕上がりの見た目が悪くなるため、職人がつきっきりで慎重に焼き色をつけます。
③下煮する
(最初の煮込み:約1時間)

素焼きした鮎を鍋に並べ、福来純の料理酒+水を同割りにし、鮎が完全にかぶるくらい注ぎます。
ここに三温糖、梅干し、酢を加え、キッチンペーパーで蓋をし、決して煮立たせないように、約1時間じっくり煮ます。
グツグツなったり、鮎同士の隙間が大きいと身が崩れやすくなるため、きっちりサイズの鍋を推奨。

常に鮎が煮汁をかぶっている状態を保ちながら、煮汁が減る度に酒と水を足し続けます
④冷まして半日~一日寝かせる
火を止め、この状態で半日〜一日かけて冷ます。
寝かせることにより、ほんのり心地よい甘さが鮎全体にしみわたります。
⑤あたり(味)を付けていく
(仕上げの煮込み:約1時間)
鮎の鍋に、井上古式醤油と福来純のみりんを加え、再びキッチンペーパーで蓋をして煮始めます。
この時も決して沸かしすぎず、一度で味を決めるのではなく、少しずつ味を足しながら約1時間煮込み。

後でさらに煮詰めることを考慮し、「ちょっと薄すぎるかな」くらいの塩梅で止めるのがコツ
減った煮汁は再び酒と水を足し、常に鮎が煮汁に浸っている状態を保ちます。
⑥煮詰めていく
蓋を外し、煮汁を鮎にかけながら、煮汁が半分くらいになるまでじっくりと詰めていきます。
⑦再び冷ます
煮汁が半分くらいになったら火を止め、また紙蓋をして冷まします。
完全に冷めたら、鮎を取り出しパットに並べておきます。
まだ熱いうちに取り出すと、せっかくの鮎が煮崩れてしまうため、急がず時間をかけて冷まします。
⑧煮汁だけをさらに煮詰める
鮎を取り出した後、残った煮汁を火にかけ、三温糖・醤油・みりんを加え、さらに半分くらいになるまで煮詰めます。
煮詰めるほどに醤油の辛さが勝ってくるため、控えめを心がけ、繊細に味を調整します。
この煮詰めた最高の煮汁を冷ました鮎にからめて、完成。

職人の魂が込められた、秋の贅沢を食卓へ
魚匠が自信を持ってお届けする
「子持あゆの梅甘露煮」

旬の恵みである子持あゆを厳選し、長年の経験を持つ職人が、半日以上もの時間をかけて付きっきりで作り上げる、まさに「魚匠の逸品」。
骨まで軟らかく、噛むほどに鮎の濃厚な旨みと卵の食感、そして梅のほのかな風味が口の中に広がる。
この手間暇かけた美味しさは、ご自宅での晩酌を格上げし、大切な方への贈答品としてもきっと喜ばれるでしょう。
秋の訪れを告げる最高の味覚
子持あゆの梅甘露煮は
数量限定でのご提供となります。
この機会に、魚匠の魂が込められた伝統の味をぜひご賞味ください。
今すぐお取り寄せで、極上の食卓を。
【原材料名】
魚(岐阜産子持あゆ)・梅干し・酒・三温糖・醤油・味醂・酢(一部に大豆・小麦を含む)
【内容量】
2尾・約200g
【賞味期限】 商品到着より30日
【保存方法】 要冷凍 (‐18℃以下で保存してください)
※解凍後は冷蔵庫で保管し、3日以内にお召し上がりください。
※開封後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。
【調理方法】
解凍は必ず、冷蔵庫内で。
できるだけゆっくり解凍してください。
そのままでもお召し上がりいただけます。
ほんのり温めていただいても美味しくお召し上がりいただけます